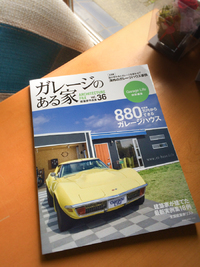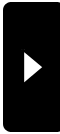2011年10月05日
浜松版エコハウス(案)。
 (+)
(+)2009年の夏、浜松版エコハウスのプロポーザルがありました。
人・建築設計所案は、最終選考には残り、入賞しました。
 (+)
(+)仕事の合間の提案で、たった2日間で仕上げたフリーハンドの図面。
プレゼンテーション・テクニックは、この図面に全く見えません。
 (+)
(+)そんな訳で、伝えたいことが、伝えられたのか心配です。
しかし、この経験は確実に人・建築設計所の力になりました。
 (+)
(+)あれから2年。
浜松市の住宅は、何かかわったのでしょうか?
 (+)
(+)今もう一度、この提案をみると、なるほどという面と、
「気軽にというにはちょっと...」というところがあります。
人・建築設計所では、エコハウスが「気軽に建てられ」て、
「気軽に住める」ように、仕様を策定し、提案しています。
【浜松版エコハウス提案書】
器は、その中に盛りつけるもの、様式や文化によって、形が変化している。液体、固体、冷たいもの、温かいもの、熱いもの、箸、スプーン、フォークとナイフ、和食、洋食、中華などなど。こうした多面的要素を踏まえ、器は、安全に、使いやすく、食べやすく、時には、おいしさをいっそう高められる。器はつまり、ユニバーサルなデザインそのものなのである。
「住まい」は、人が入る器。器と同じように、人に対してのユニバーサルデザインを考えることからはじまる。人が住む上で、大切にしたい3要素がある。①「物理的」に守られていること。②「生理的」に優しいこと。③「心理的」に安心できること。エコハウスという要素は、この一部と考えることを忘れてはならない。
さて、「浜松の民家」を考えると、夏向きの家だったことが分かる。夏場は、たえず南西からの風があり、これを取り入れるために建物の形状が、風を招き入れるように雁行していたり、袖壁が出ていたりしている。取り入れた風は、北東側へ上手に抜けるよう、ふすまなどを開け放し、一体の空間となることで、風通しを良くしている。また、床下の面戸板を解放することで、地熱を利用して冷やされた空気が、屋内へと侵入し、ひんやりと感じられる。外気を一旦冷やしてから取り入れることで、湿度を低下させる働きもある。もちろん断熱材はなく、夜間の放射冷却により、建物の材料はすぐに冷やされる。また、調湿性能の高い仕上げ材、畳、土壁、タタキ土間、ムクの板、障子や襖など、人の触れる範囲のものが、さらりとして気持ちがよい。土壁やタタキ土間といった左官材料も、蓄熱容量が大きく、低温安定型として夏場に適したものである。また、外構・植栽では、西日対策として槇(ホソバ)囲いがある。これは、冬場の季節風の抑制にも一役買っている。
つぎに、冬場については、床下の面戸板を閉じ、槇囲いによる季節風対策。他の地域同様、局所暖房によって堪えしのぐ家である。しかし、太平洋側の気候であることから、冬場は晴天が続く。この熱を如何に取り入れるか、命題となっていた。こうした背景から、この地では太陽熱利用の研究が進んだものと考えられる。同様に、今後は太陽光発電の採用も加速するであろう。
浜松版エコハウスは、こうした気候風土から派生した歴史的側面から、北方系の高断熱高気密住宅をまねるのではなく、南方系の高性能高機能住宅とすることが、導き出される。よって、次世代省エネルギー型住宅を造るのでは、浜松版エコハウスを創り出すことにあらず。遮熱、日射遮蔽、通風、大蓄熱容量、気化熱、地熱、潜熱などを使い夏場対策を行い、気密性能、太陽熱、バイオマス燃料を使った冬場対策、そして、年間を通した太陽熱、太陽光発電の恩恵を得る。そして、この実測実験、地域発信を行う。これが、真の浜松版エコハウスの役割であると考える。
Posted by たかだい at 12:18│Comments(0)
│イエ
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。