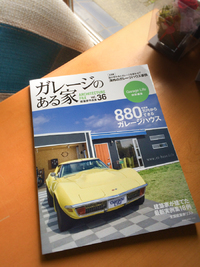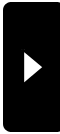2007年04月10日
素材を考える。
自然素材は、今や欠かせない存在になっています。自然素材というと、それだけで良いイメージがありますね。しかし、実際に使うとなると、それなりに覚悟することもあります。
不定期な連載ですが、こうした素材を少し掘り下げてみようと思います。第1回目の今回は、この自然素材がブームとなった経緯を考えてみようと思います。
 「自然素材」という言葉がいつ頃できたのか、定かではありませんが、以前は「新建材」に対して「天然素材」といっていたと思います。1996年に住宅関連の書籍に、この言葉が登場しています。ボクの記憶では、1991年竣工の神長官守矢資料館(藤森照信氏+内田祥士氏の設計)が、建築家の作品では走りだったと思います。もちろん土壁を多用した建築家もいましたが、藤森氏のそれは、公共性の高い建築ではめずらしく、自然素材を斬新に使ったもので、鮮烈だったのです。それまで新建材へ邁進していた業界が、少し揺り戻したような感覚がありました。しかし、多くの住宅産業では、自然素材を扱うことがありませんでした。
「自然素材」という言葉がいつ頃できたのか、定かではありませんが、以前は「新建材」に対して「天然素材」といっていたと思います。1996年に住宅関連の書籍に、この言葉が登場しています。ボクの記憶では、1991年竣工の神長官守矢資料館(藤森照信氏+内田祥士氏の設計)が、建築家の作品では走りだったと思います。もちろん土壁を多用した建築家もいましたが、藤森氏のそれは、公共性の高い建築ではめずらしく、自然素材を斬新に使ったもので、鮮烈だったのです。それまで新建材へ邁進していた業界が、少し揺り戻したような感覚がありました。しかし、多くの住宅産業では、自然素材を扱うことがありませんでした。
1996年晩秋、OMソーラー協会が主催する『「自然素材を詩う」これからの住まいづくりに役立つ使える自然素材フェア』が、東京・六本木のアクシスギャラリーで開かれています。この展示会は、日本全国の伝統的な自然素材を丹念に調べ、そのサンプルとともに展示、エコロジーを訴えかけるものでした。こうした資料は、当時、殆どありませんでしたので、展示担当者の苦労が伺えました。多くの知識人が来場し、自然素材ブームは、これが火種になったと確信しています。
このOMソーラー協会は、実のところボクの古巣です。「自然派の住宅」を20年近くも牽引する役割を果たしていたと思います。しかし、本業のソーラーシステムではなく、なぜ自然素材だったのか。自然回帰こそエコロジーだったと書けばキレイですが、そこには地元に根ざしている地域工務店の生き残りをかけていたという側面も見えました。また、室内空気質汚染などによるシックハウス症候群が言われはじめた頃とリンクしています。自然素材が使えるのだということを広め、できるだけ悪いもの(新建材)を取り除くための仕掛けだったと、ともとれます。いずれにしても、新建材へ走る建築・建設業界へのアンチテーゼであり、社会的使命を果たしたことは確かです。
そして現在、自然素材を謳わない住宅は、殆どなくなりました。猫も杓子も自然素材です。10年ほどの期間の間に、時代の先端になったのです。しかし、一人歩きした自然素材を、もう一度見直す段階に差し掛かっていると思います。こうした目で、素材を拾い上げてみたいと思います。
不定期な連載ですが、こうした素材を少し掘り下げてみようと思います。第1回目の今回は、この自然素材がブームとなった経緯を考えてみようと思います。
 「自然素材」という言葉がいつ頃できたのか、定かではありませんが、以前は「新建材」に対して「天然素材」といっていたと思います。1996年に住宅関連の書籍に、この言葉が登場しています。ボクの記憶では、1991年竣工の神長官守矢資料館(藤森照信氏+内田祥士氏の設計)が、建築家の作品では走りだったと思います。もちろん土壁を多用した建築家もいましたが、藤森氏のそれは、公共性の高い建築ではめずらしく、自然素材を斬新に使ったもので、鮮烈だったのです。それまで新建材へ邁進していた業界が、少し揺り戻したような感覚がありました。しかし、多くの住宅産業では、自然素材を扱うことがありませんでした。
「自然素材」という言葉がいつ頃できたのか、定かではありませんが、以前は「新建材」に対して「天然素材」といっていたと思います。1996年に住宅関連の書籍に、この言葉が登場しています。ボクの記憶では、1991年竣工の神長官守矢資料館(藤森照信氏+内田祥士氏の設計)が、建築家の作品では走りだったと思います。もちろん土壁を多用した建築家もいましたが、藤森氏のそれは、公共性の高い建築ではめずらしく、自然素材を斬新に使ったもので、鮮烈だったのです。それまで新建材へ邁進していた業界が、少し揺り戻したような感覚がありました。しかし、多くの住宅産業では、自然素材を扱うことがありませんでした。1996年晩秋、OMソーラー協会が主催する『「自然素材を詩う」これからの住まいづくりに役立つ使える自然素材フェア』が、東京・六本木のアクシスギャラリーで開かれています。この展示会は、日本全国の伝統的な自然素材を丹念に調べ、そのサンプルとともに展示、エコロジーを訴えかけるものでした。こうした資料は、当時、殆どありませんでしたので、展示担当者の苦労が伺えました。多くの知識人が来場し、自然素材ブームは、これが火種になったと確信しています。
このOMソーラー協会は、実のところボクの古巣です。「自然派の住宅」を20年近くも牽引する役割を果たしていたと思います。しかし、本業のソーラーシステムではなく、なぜ自然素材だったのか。自然回帰こそエコロジーだったと書けばキレイですが、そこには地元に根ざしている地域工務店の生き残りをかけていたという側面も見えました。また、室内空気質汚染などによるシックハウス症候群が言われはじめた頃とリンクしています。自然素材が使えるのだということを広め、できるだけ悪いもの(新建材)を取り除くための仕掛けだったと、ともとれます。いずれにしても、新建材へ走る建築・建設業界へのアンチテーゼであり、社会的使命を果たしたことは確かです。
そして現在、自然素材を謳わない住宅は、殆どなくなりました。猫も杓子も自然素材です。10年ほどの期間の間に、時代の先端になったのです。しかし、一人歩きした自然素材を、もう一度見直す段階に差し掛かっていると思います。こうした目で、素材を拾い上げてみたいと思います。
Posted by たかだい at 22:26│Comments(0)
│自然素材